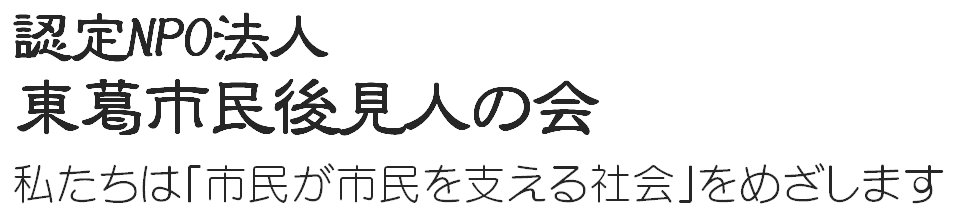成年後見制度を知りたいあなたに説明します!
- 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人(=本人)に対して、身上保護を通して法律面や生活面での支援を行い、詐欺や悪徳商法から本人を守り、本人のために財産管理を行うしくみです
- 成年後見制度のしくみは次に掲げる三つの理念をベースに組み立てられています
① 自己決定権の尊重(本人が自分で判断し決めることを尊重)、② 現有能力の尊重(本人が有している能力を最大限に活用)、③ノーマライゼーション(家庭や地域で、健常者と同様な通常の生活を送れるように支援) - 成年後見制度の下で、本人(=被後見人)に対する支援活動を後見人が始めるためには、本人や家族等が家庭裁判所への申立を行い、家裁で後見等開始の審判を通じて、後見人が選任され、法務局での登記が完了して初めて本人への支援が始まります
*前項の手続きについては法定後見と任意後見では違いがありますし、詳しく知りたい方は家庭裁判所の後見サイトをご覧ください
http://https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp00/koukenp1/index.html
任意後見制度の利用をお考えのあなたに説明します!
- 任意後見制度の利用には、任意後見契約の締結と、契約を発効させるための任意後見監督人の選任申立を将来家裁に行うツー・ステップが必要です。
- 任意後見契約を結べる方(委任者=本人)とは、将来判断能力が不十分になった時にご自身が望む生活を送れるよう、判断能力が十分にある今、必要な任意後見契約と関連諸契約を検討したいと考える方です。
- 法定後見とは違って、任意後見契約では本人自ら任意後見人(=受任者)を選任し、相対で任意後見契約と関連する諸契約(見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約、いざというときの意思表示、遺言等)を公正証書にて締結します。
- 契約を締結しても任意後見は開始せず、本人の判断能力が十分でなくなった時に、本人や親族、あるいは契約受任者が家裁に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見監督人選任の家裁による審判を通じて、初めて任意後見契約が発効し、任意後見人が支援活動を開始します。
- 任意後見契約は発効前の報酬支払はありませんが、発効後に任意後見人と任意後見監督人への報酬支払が生じます
- 任意後見契約との関連で結ぶ諸契約の詳細については、当会パンフレット「老後の安心プラン」をご覧ください
法定後見制度の利用をお考えのあなたに説明します!
- 法定後見制度の利用は家裁への申立が必要です
- 法定後見を利用する対象者(=本人)は認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な方でなければなりません
- 申立てができる方(申立人)は本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、区市町村長、検察官です
- 申立てに当たっては、本人の判断能力が不十分であることを証する医師の診断書が必要です
- 申立人は希望する後見人等候補者事情説明書を提出できますが、家裁は必ず同候補者を選任するとは限らず、違う後見人が選任されても申立てを取り下げできません
- 法定後見人には身上保護支援内容や収支報告、財産状況に関する定期報告を毎年家裁に提出する義務があり、家裁が決める報酬を本人が後見人に支払います
後見人の違い(専門職後見人と市民後見人)を説明します!
- 成年後見人になるには特に資格は必要なく、家裁が適任であると判断する人が後見人に選任されます。弁護士・司法書士・社会福祉士からなる専門職後見人と親族後見人、市民後見人が主な担い手です。成年後見人制度の利用は家裁への申立が必要です
- 専門職後見人が後見人として行う支援内容は基本的には市民後見人と同じです。しかしながら、専門職の場合は、その専門領域毎に自ずと強みに濃淡があり、法的なトラブルを抱える被後見人にとって弁護士後見人は頼り甲斐があることでしょう。他方、時間単価の高い専門職後見人の場合、その専門をもって生計を立てているが故に、身上保護に重きを置いて被後見人に寄り添い、被後見人が望むきめ細かな支援をバランスよく行うためには時間を割けないかも知れません
- 市民後見人には、男女の別なく、現役世代からOB世代まで幅広い年代からなり、様々な分野での職歴、専門知識を備えた多様な人材が集っています。多様な人材の組み合わせ(=後見事務担当者チーム)による被後見人の支援活動を、組織として実現する仕組みが法人後見人としての当会の法人後見活動です
後見人の違い(自然人後見人と法人後見人)を説明します
認定NPO法人東葛市民後見人の会(=当会)は家裁の審判により、法人後見人として受任しています。ここでは一個人(=自然人)として後見人を受任することと、当会が法人として受任(=法人後見人)することの違いは何なのかを説明します。
- 個人には寿命や個人的事情が伴うが、法人としての当会活動は持続的で終わりがない
- 法人としての当会は後見事務担当者3人によるチームを事案毎に編成し後見活動を行う
- 法人としての当会会員=後見事務担当者には様々な経歴・知識やノウハウがあり、3人で組むチームによる支援活動も多様でかつ柔軟な対応が可能となる
- 法人としての当会では、財産管理をすべて一個人が行うリスクを排し、チームと財産管理室の間で財産の分別管理を行うので、不正を許容しない内部牽制機能が働く
- 法人としての当会では、後見事務担当チームが毎月作成・報告する活動報告書を事務管理室がチェックし、年一度家裁へ提出する定期報告も法人として審査し承認している